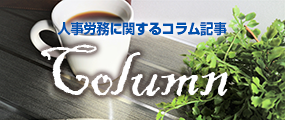ハラスメント対策
ハラスメントと言えば、以前はセクシュアルハラスメント(セクハラ)、パワーハラスメント(パワハラ)でしたが、いまはマタニティーハラスメント(マタハラ)が主流と言われています。ハラスメント防止の法令整備も、セクハラは1990年4月(女性)、2007年4月(男女)、マタハラが2017年1月、パワハラが2020年6月に施行されています。その他のハラスメントにはモラハラ(道徳)、スメハラ(においが原因。女性の香水や体臭など)も一般化しています。
会社がとるべき施策
ハラスメント対策は原則会社内での対応を義務づけられています。では、どのような対策が必要でしょうか?
当事務所では下記項目を柱にハラスメント対策をご提案しております。
ハラスメントの知識と理解と社員への周知・啓発
なぜハラスメント対策が必要なのか
職場におけるハラスメントは、社員のメンタル不調や離職、企業の信用失墜など、大きなリスクにつながります。
法改正により、全ての事業主にハラスメント防止措置が義務化され、今や「知らなかった」では済まされません。
しかし、制度を整備するだけでは不十分です。
社員一人ひとりが正しく理解し、実際に行動できる環境づくりが重要です。
就業規則などへの禁止規定、相談対処方法、懲戒の明文化
ハラスメントを防止するには、単なる啓発や研修だけでなく、就業規則に明確な禁止規程と懲戒処分を定めることが不可欠です。
- 社員に「何が禁止される行為か」を明確に示す
- 違反した場合に「どのような処分があるか」を明文化する
- トラブル発生時に、会社が毅然と対応できる根拠となる
👉 つまり、就業規則は 「会社を守る盾」であり、社員を安心させるルールブック なのです。
相談窓口の設置と体制整備
相談窓口は“社員の安心と会社の防御線”
ハラスメントの発生を未然に防ぎ、発生時に迅速かつ適切に対応するには、社内の相談窓口の設置とその運用体制の整備が不可欠です。弊所でも外務の相談窓口を設置いたします。
- 社員が安心して相談できる窓口
- 相談内容を正しく記録・管理する仕組み
- 適切な調査・対応フローの整備
これにより、トラブルの早期解決と会社の法的リスク低減を両立できます。
相談手順等のマニュアルの作成
ハラスメント相談体制のマニュアル作成が必須です。弊所でもマニュアル作成のお手伝いをいたします。